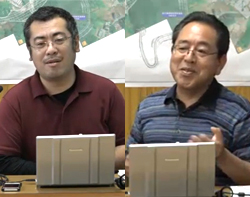-
館報まっさき 第366号(令和7年6月20日発行)
 末崎まちづくり協議会総会が開催されました 本年度の事業は、ラージボール卓球と体協卓球、ボッチャがほぼ毎週。9月に敬老会、10月に町民文化祭を計画しています。7月にスカットボール・輪投げ大会と茶道教室、9月にグラウンドゴルフ大会、1...
末崎まちづくり協議会総会が開催されました 本年度の事業は、ラージボール卓球と体協卓球、ボッチャがほぼ毎週。9月に敬老会、10月に町民文化祭を計画しています。7月にスカットボール・輪投げ大会と茶道教室、9月にグラウンドゴルフ大会、1... -
館報 まっさき 第365号(令和7年5月20日発行)


 経験のない方でも気軽にどうぞ! 卓球、ボッチャ 参加者募集中 4月からふるさとセンターでお世話になることになり、初めて気づいたことがたくさんあります。 その中の一つが卓球の練習が継続して行われているということです。 まちづくり...
経験のない方でも気軽にどうぞ! 卓球、ボッチャ 参加者募集中 4月からふるさとセンターでお世話になることになり、初めて気づいたことがたくさんあります。 その中の一つが卓球の練習が継続して行われているということです。 まちづくり... -
令和7年館報まっさき 4月号


 <末崎地区公民館改め 末崎まちづくり協議会> 令和七年三月二十五日に「末崎まちづくり協議会」の設立総会が開かれ、すべての議案について承認され、協議会を四月一日から設置することになりました。 これまで末崎町では、末崎町がよりよく発展するよう...
<末崎地区公民館改め 末崎まちづくり協議会> 令和七年三月二十五日に「末崎まちづくり協議会」の設立総会が開かれ、すべての議案について承認され、協議会を四月一日から設置することになりました。 これまで末崎町では、末崎町がよりよく発展するよう...
大船渡市末崎町中森鎮座 熊野神社式年大祭
令和6年10月19日収録
気仙の人々に学ぶ(3.11と今、そして明日)
KK2教材
(動画・オンラインキャリア相談 等)を
お気軽にご利用ください
東京・霞が関にある「デジタル公民館KK2」では動画教材等を提供しています。
※動画視聴の多くは無料です。一部有料の参加型プログラムがあります。
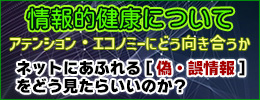
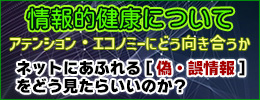
情報的健康について―アテンション・エコノミーにどう向き合うか
視聴無料
ネット世界にあふれる情報。そこには、炎上、分断、誘導、中毒といった負の要素もあふれています。そんな中、「情報的健康」を実現するにはどうすればいいのか?
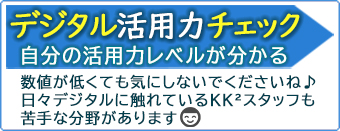
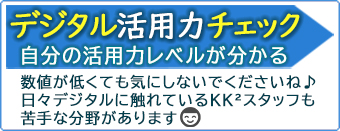
デジタル活用力チェック
視聴無料
現時点でデジタルをどのくらい活用できているかをチェックできます。
「デジタル社会の基礎的知見」「コンピュータ活用力」「インターネット活用力(基礎)」「インターネット活用力(応用)」「デジタル社会のリスク」「デジタル社会進展に必要な知見、の6カテゴリーで測ります。
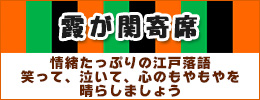
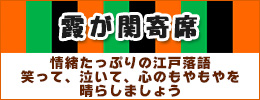
寄席
視聴無料
東京霞が関で行われている寄席を期間限定で動画視聴できます。情緒たっぷりの江戸落語で笑って、泣いて、心のもやもやを晴らしませんか。
「真田小僧」「らくだ」等
※視聴できる演目はKK2のwebページでご確認ください。
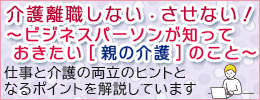
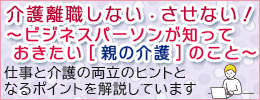
介護離職しない・させない!~ビジネスパーソンが知っておきたい「親の介護」のこと~
視聴無料
仕事と介護の両立にあたって様々な悩みに直面した時、正しい情報を得て、自分が望む選択ができることが大切です。事前に介護についての知識があれば、あわてずによりよい選択ができる可能性があります。急に親の介護をはじめることになった!というスタート時期に役立つ基本的な知識についてわかりやすく解説します。
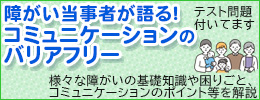
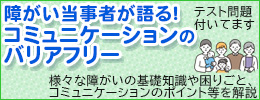
障がい当事者が語る!コミュニケーションのバリアフリー
視聴無料
障がい者を取り巻く状況、さまざまな障がいの基礎知識や困りごと、コミュニケーションのポイント等を、障がい当事者が講師となって解説するこれまでにないプログラムです。17本シリーズとなっており、それぞれ1本で完結する内容ですので、ご興味あるタイトルを選んでお気軽にご視聴ください。
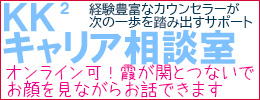
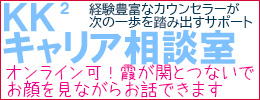
キャリア相談室
1回60分、7,700円(税込)
社会で働く人々が自らの適正、能力、経験などに応じてワークライフ(職業生活)を設計する事をキャリアデザインと言いますが、個人がスキルアップ(能力開発)やキャリアチェンジ(職業選択)を効率よくできるように、個別に第三者である専門資格を持ったカウンセラーと相談を行う事です。オンラインで相談可です。